炭素線治療場の線質・線量の評価
遠藤 暁
1.炭素線治療
|
|
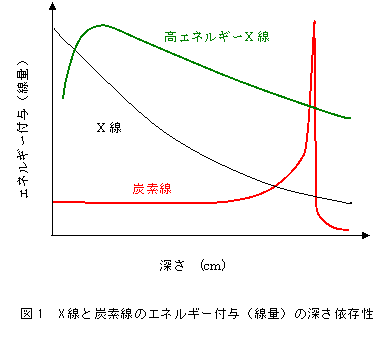 放射線によるがん治療は、近年目覚しい進歩を遂げている。その中でも代表は、炭素線を用いた重粒子線治療である。重粒子線は物質中でクーロン相互作用(電気的反発力)により、エネルギーを物質へと与え、エネルギーを失い減速する。この減速過程をつぶさに観測すると、静止直前において最も大きなエネルギー付与を行い、静止直前図1に示すようなピーク構造となる。このピークをブラッグピークと呼ぶ。比較のため、X線のエネルギー付与の深さ分布を示している。図よりX線では、物質表面で線量が高く深部においては減少するのに対し、重粒子線では表面において線量が小さく、深部に行くに従い大きくなることがわかる。したがって、このブラッグピークを腫瘍などの治療部位に合わせることで、選択的に腫瘍細胞を殺せる。さらに、線量の集中性という特徴を持つ重粒子線は、従来のX線やγ線を用いた治療と比較し、治療部位の局所制御を可能にする点で有効なほか高LET(線エネルギー付与)という放射線の生物学的特異性により、X線治療などで治療が困難な、線がんや骨肉種、悪性黒色腫なども制御が可能である。
放射線によるがん治療は、近年目覚しい進歩を遂げている。その中でも代表は、炭素線を用いた重粒子線治療である。重粒子線は物質中でクーロン相互作用(電気的反発力)により、エネルギーを物質へと与え、エネルギーを失い減速する。この減速過程をつぶさに観測すると、静止直前において最も大きなエネルギー付与を行い、静止直前図1に示すようなピーク構造となる。このピークをブラッグピークと呼ぶ。比較のため、X線のエネルギー付与の深さ分布を示している。図よりX線では、物質表面で線量が高く深部においては減少するのに対し、重粒子線では表面において線量が小さく、深部に行くに従い大きくなることがわかる。したがって、このブラッグピークを腫瘍などの治療部位に合わせることで、選択的に腫瘍細胞を殺せる。さらに、線量の集中性という特徴を持つ重粒子線は、従来のX線やγ線を用いた治療と比較し、治療部位の局所制御を可能にする点で有効なほか高LET(線エネルギー付与)という放射線の生物学的特異性により、X線治療などで治療が困難な、線がんや骨肉種、悪性黒色腫なども制御が可能である。
2.当研究室での研究
重粒子線治療はその有効性の反面、重粒子線治療はX線を用いた治療と比較して、歴史が浅く、解決すべき問題も残されている。その1つに2次粒子の問題がある。2次粒子とは、炭素線が人体中やビームモデレータ中において発生する散乱線のことで、その多くはフラグメントと呼ばれる入射炭素線が物質中で壊れた原子核の破片である。炭素線の場合、H、He、Li、Be、Bがフラグメント粒子として生成される。また、2次粒子中には、中性子(n)も生成される。このような、2次粒子は、治療部位への線量集中性を持たず、本来照射すべきでない正常組織へ線量を与えることとなる。したがってこの2次粒子の線量が高ければ、治療照射に考慮する必要が生じる。我々は、このような2次粒子の線量・線質を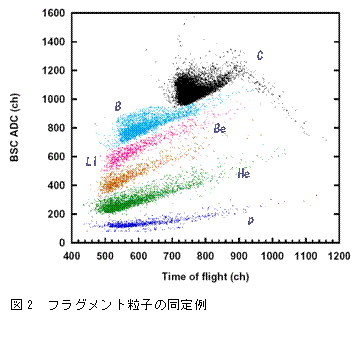 評価するため、測定手法や測定器の開発を行っている。現在行っている測定法は、マイクロドシメトリと呼ばれる手法を応用したものである。マイクロドシメトリでは、生体等価壁・生体等価ガスを使用したガス比例計数管(TEPC)を用いて、微視的な(1μm程度の)生体内で放射線が付与するエネルギーを模擬測定する。したがって、放射線場の線量と線質を同時に測定できるという利点がある。このTEPCにシンチレーションカウンターと半導体検出器を併用することで、測定対象となる粒子の種類を同定した後にエネルギー付与分布を決定する。図2にシンチレーションカウンターを用いた飛行時間による粒子識別の測定例を示す。このような測定手法が確立すれば、粒子線治療のみでなく宇宙環境中における被曝線量評価へも利用できる可能性がある。
評価するため、測定手法や測定器の開発を行っている。現在行っている測定法は、マイクロドシメトリと呼ばれる手法を応用したものである。マイクロドシメトリでは、生体等価壁・生体等価ガスを使用したガス比例計数管(TEPC)を用いて、微視的な(1μm程度の)生体内で放射線が付与するエネルギーを模擬測定する。したがって、放射線場の線量と線質を同時に測定できるという利点がある。このTEPCにシンチレーションカウンターと半導体検出器を併用することで、測定対象となる粒子の種類を同定した後にエネルギー付与分布を決定する。図2にシンチレーションカウンターを用いた飛行時間による粒子識別の測定例を示す。このような測定手法が確立すれば、粒子線治療のみでなく宇宙環境中における被曝線量評価へも利用できる可能性がある。